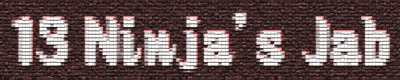
―――それは、ただの気まぐれだったと思う。
慈悲とか慈愛とか、僧侶たちが言うようなそんな心を持っていたわけではない。
神の存在を否定する気はないが、だからといってその神に気に入られるために何かしようという気はない。
何か、見返りを求めたわけでもない。
そいつは見るからにみすぼらしく、俺に対して何らかの利益をもたらせてくれるようには見えなかった。
だから、ただの気まぐれ。
自分のねぐらの前で倒れられて、そのまま死体になられると気分が悪いとか、そんなことしか思わなかった。
それに、他にすることもなかった。
だからそいつを―――こともあろうにエルフの棲む森に侵入し、途中で力尽きた愚かな人間の男を助けたのは、本当にただの気まぐれ。
何もしない毎日にも飽きてきたので、たまには違ったことをしてみようと思った。ただそれだけのこと。
しかしそのただ一度の気まぐれが、その後の俺の全てを変えることになろうとは、百五十年生きた俺でも全く予想すら出来なかった。
その男は、オックスと名乗った。
「オックス(雄牛)? 人間とは変わった名をつけるものだな」
「いや、本名ではない。まあ、称号とかそういった類のものだな」
オックスは目の前にある肉を食らい、果実酒を飲みつつ話を続ける。
「しかし、助かった。本当に感謝している」
「気にするな。大したことはしていない」
謙遜ではない。
そんなことをする理由もない、というか実際大したことはしていない。
倒れていたオックスをとりあえず家の中に運び込みんで様子を見てみたのだが、その体には外傷もないしこれと言って異常も見受けられなかった。
何のことはない、空腹で倒れ伏していたらしい。
今は若干衰弱しているようだか、数日の間休養を取れば元通り健康な身体に戻るだろう。
「何が目的でこの森に来たのかは知らんが、手ぶらと言うのは―――」
「ああ、いや。荷物はそれなりにあったのだがな。途中で手放してしまった」
はっはっは、とオックスは衰弱しているくせにやけに快活に笑いながらそんなことを言った。
「獣にでも襲われたか?」
「まあ、そんなところだな」
悪びれもせず、そんな返事を返してくる。
人間とは、こういったものなのだろうか。
里で老人たちに聞いた人間とは「野蛮で愚かな、強欲な生き物」とのことだったのだが、少なくともこの男からはそんなところは感じられない。
「まあ、なんにせよ怪我一つせずに済んだのは幸運だったな。このあたりにも肉食の獣はいる。あのまま倒れていたら奴らの糧になっていただろう」
「うむ、面目ない。いくら感謝しても、し足りないな。えーと……」
「サイランだ」
「サイラン。この恩にはきっと報いよう」
「まあ、期待しないでおこうか」
なんというか、この男には邪気がない。
人間とはこういうものなのだろうか。
それともこの男が特別なのか。
「何もないが、食料の貯えならまだある。出て行く気になるまでここにいてくれてもかまわんぞ」
「それはありがたい……が、いいのか? 人間をエルフの森に置いておいても」
この森に住むエルフとしては、一刻も早くこの男を森の外へと追い出すべきなのだろうが―――
「かまわんさ」
そう、かまわない。
「俺もお前と同じはぐれものだ」
そういった俺の答えを聞いて、オックスはほう、とつぶやいて興味深そうな表情を見せた。
今考えてみればどうして人間などに話そうと思ったのかはわからない。
酒が回っていたのかもしれない。
とにかく、俺は目の前にいる男に自分のことを話し始めた。
俺は、氏族の中でもそれなりの地位を持つ家に生まれた。
エルフは人間と比べて生殖能力が低いため、子供は大事にされる。
俺もそれは例外ではなく、生まれたときには氏族全員で宴を開いたと言う話も聞いたことがある。
周囲に見守られ、同年代の友人たちと何不自由も無く育っていった。
そして、成人。
この時も宴が開かれ、生まれて初めて酒を飲んだ。
幸せだった。
それまでのように宝物のように扱われることはなくなるが、一人前のエルフとして認められるようになり、それまで世話になっていた氏族のものたち と同じ立場に立てるようになる。
そして、俺を生み育ててくれた両親にその恩を返すことが出来る。
それがこの上なく嬉しかった。
今思い出してみれば、それがあの森での最後の幸せな記憶になる。
エルフが魔術を使うことは、鳥が空を飛ぶのと同じようなもの。
成人したエルフは自らの魔術の質を見極め、その分野の先達の教えを乞う。
あるものは魔術師として、人間たちの間では失われつつある魔具の製作に携わり、その中でも優れたものは氏族の根幹たる『大樹』を育て、守るための儀式に参加する。
またあるもおのは獣を操り、樹木を友として森の中を巡回する。
それは数千年―――ひょっとしたら一万年以上の間、あの大災厄が起きても変わらなかったエルフの在りかた。
そしてその技を持って氏族へと貢献するのだ。
しかし、俺にはそれが出来なかった。
指先から魔法の矢が飛ぶことも無かったし、植物を操ることも出来なかった。
それどころか、初歩的な光の魔術すら使えなかった。
努力はした。
教師となってくれたエルフ―――俺の父親も、優れた魔術師だった。
準備も手順も、全ては完璧だった。
ただ結果だけが現れなかった。
それは教師を変えても、習得する魔術を変えてみても同じこと。
動作も発音も、その全てを完璧にトレースすることは出来たが、それによって何かの魔術が発現することは決してなかった。
そして、俺の居場所は無くなった。
それまでの期待が大きかったためか、氏族の皆は俺のことを陰で笑い、母親は俺と顔をあわせるたびに恨み言を言うようになった。
父親は俺に魔術の素質が無いとわかって以来、顔をあわせようとすらしなくなった。
それでも一応成人した俺は森の中を巡回する任についたが、何の魔術も使えない半端ものと一緒にいようと言う酔狂なエルフは存在しない。
俺はただ一人、誰も赴かないような森の端を自らの管理区域として割り与えられた。
俺に区域を与えたレンジャーたちの長は「区域内で危険に直面する氏族のものがいたら助け、報告しろ」と命じていたが、それが詭弁であることは 明らかだった。
大災厄が起きて以来、荒れ果てた外に出ようとするエルフなどいるわけも無く、俺の管理区域に助けるべきエルフがいるわけがない。
つまり俺は、部族のものと関わることを望まれなかったのだ。
「そんなわけで、俺はこの小屋をねぐらにして過ごしているわけだ」
「一人でか?」
「ああ、そうだな。年に数回は長に報告をしにいくが、それだけだ。氏族の皆が住むところには、ここ十年ほど戻っていないな」
今更それをどうとは思わない。
問われたから答えただけだと言うのに、オックスはなぜか不快そうな表情をしていた。
「どうした?」
「つまり、お前の親や氏族の者たちは魔術が使えないお前を捨てたと言うことか」
「そうなるな」
確認するまでも無いだろう。
先ほどの俺の話を短くまとめるとそういうことになる。
「お前はそれでいいのか? 魔術が使えないだけで、お前個人が何か問題を起こしたわけではないのだろう?」
「そうだな、確かに不満が無いと言えば嘘になる」
それは事実だ。
「それなら、なにかするべきだろう。魔術が使えなくとも、氏族に貢献すれば―――」
「いや、いいんだ」
己のことではないにもかかわらず、声を荒げて怒るオックスを制してそう言う。
「氏族から離れて、外から見てみてやっとわかったこともある」
「それは?」
「エルフたちの醜さだよ」
「―――まるで自分がエルフじゃないみたいな言い方だな」
「ん? そう言えばそうだな」
オックスに指摘されてはじめて気づいたが、確かにいまの俺の言葉はおかしかったかもしれない。
俺も氏族で生まれたエルフであることに変わりは無い。
しかし、その言葉は口に出してみるとやけに自然に受け止められた。
「それで、『醜さ』と言うのは?」
「ああ。さっきも説明した通り氏族では魔術の力や技術を重視する。魔術以外の力は認めず、魔術の素養が低い他の種族を下賎で野蛮な種族と蔑み嘲笑う」
そう、それがエルフの在りかた。
俺がここに追いやられたのは『誇り高き種族』エルフであるのに、魔術の素養が無いから。
「それが『醜い』と?」
「ああ」
一人で過ごしてみて、わかった。
ただひたすら強くなるために、研鑽を積む姿が間違っているとは思わない。
森の外ほどではないにせよ、荒廃したこのヴァルカニアで過ごすためには力が必要だ。
力が無ければ生きていけないのは事実だろう。
そして、その『力』のうち最も効率のいいものは魔術だ。
甲冑を身に纏い、巨大な剣を携えた兵士が何人攻めてこようと魔術師の火球一つで地に伏せる。
森の獣が凶暴化することもある。
それが飢えのためなのか、何か別な異変の影響なのかはわからないが、熊や狼と言った獣が集落にやってくることもある。
そんな時はまず剣を持ち鎧を着たものたちが獣を足止めし、その後ろから魔術の一撃で葬り去る。
剣の嵐や屋の雨を、その分厚い筋肉と毛皮で弾き返す獣であっても魔術師たちの指先から放たれる電撃の前にはただの肉塊と化す。
そんな強大な力を身につけるために、エルフたちは魔術の業を磨き続ける。
効率のいい破壊の方法、より強大な力を持つ魔術を習得するために鍛錬を続ける。
それは正しいことだと言う。
この世界で生き延びるためには力が必要だと。
だから魔術を身につけろと。
人間たちを凌駕する魔術を見につけるために研鑽を積めと長老たちは言い、氏族のものはそれに従う。
しかし、それは。
その姿を見て俺は―――
「ただ『力』のみを追い求める姿はどうしようもなく醜く、愚かなことだと思う」
それが俺の正直な気持ちだった。
そう。ただひたすら魔術に固執するその姿は、エルフが忌み嫌う愚かな人間、あの『大災厄』を引き起こした愚かな人間と同じ道をたどっているようにしか見えない。
エルフは愚かな人間たちとは違うと言う。
その根拠がわからない。
人間は魔術の結晶たる蝋燭の都市にこもり、数十年で身にあまる強大な力を身につけ、自滅した。
エルフもそれと同じ道をたどっているのではないか。
ただ都市ではなく森にこもり、その破滅が訪れるまでの期間が長いだけではないのだろうか。
俺は常日頃考えていたことを一つ残らずオックスにぶつけていた。
考えてみればこんな話を誰かにするのは初めてだ。
それを初対面の、しかも人間にすると言うのはおかしい話かもしれないが、俺の言葉は止まらず、オックスもただ静かに俺の言葉を聞いていた。
そしてその冷静な表情を見るうちに、思わず興奮してしまっていた俺の意識もだんだんと冷めていく。
「……すまん」
冷静になってみると、途端に恥ずかしく思えてきた。
しかも俺はオックスに、人間に『愚かな人間』などと言う言葉を連呼してしまった。
これでは俺自身が醜いと言ったエルフたちと何も変わりが無い。
だがオックスは俺の言葉に気分を害した様子も無く、きわめて平静な様子で言葉を返してきた。
「詫びることは無い。我々人間は愚かな生き物だし、あの『チキン・ザ・マンデル』の愚かさは何者をも上回るだろう」
「しかし……」
「罪を犯したのだから罰を受ける、それは当然のことだ。あの『チキン』はこのヴァルカニアに『大災厄』をもたらした。その罰としてその命を落とし、同族の者たちが愚かもの呼ばわりされると言うのであればそれは当然のことだ」
そういうオックスの目は澄んでいて、その言葉が本心であることは俺の目からみても明らかだった。
そんなオックスを見て、俺は自然と口を開く。
「いや、詫びさせてもらおう。人間は愚かなのかもしれないが、少なくともお前は聡明だ」
森にこもり、ただ力をつけることしか頭に無いエルフよりも。
言葉には出さなかったが、そんな気持ちを込めてそう言って頭を下げると、オックスは慌てて俺に声をかけた。
「俺だって様々な罪を犯した。お前にそこまで言われるような男ではない」
「しかし―――」
反論しようとした俺の声をさえぎり、オックスは言葉を続ける。
「それに、俺は人が入ることを許されないこの森に迷い込んで力尽きるような愚か者だ。いまはようやく一心地ついたが、まだ身体が本調子に戻ったとは言い難い」
「それならここで休んでいけばいい。さっきも言ったとおり、ここには他のエルフが来ることもない。身体が元通りになるまではゆっくりしていてくれて構わない」
「それはありがたいんだが―――」
そう言った後オックスは、まるで子供のような笑顔を浮かべるとこう言った。
「どうせやっかいになるのなら、友の家に厄介になるほうが気が休まる」
「ああ」
オックスの言いたいことは理解できた。
氏族の皆に知られればまた何を言われるかはわからない。
それでも、考えてみればそれは愉快なことだったし、何より俺自身がオックスに応えたかった。
「遠慮せずゆっくりして休んで行ってくれ。わが友よ」
その日、俺とオックスは友となった。
オックスがやってきて、一月近い時が流れようとしていた。
衰弱していたオックスも今ではだいぶ回復し、日常生活ではなんの問題も感じさせないようにはなった。
「―――三匹目」
俺の弓から放たれた矢は、狙いたがわず野兎に命中する。
「こんなところかな」
今朝、備蓄していた食糧を見てみたら、量が少し心もとないことになっていた。
そんなわけで俺は狩りをしている。
別に特別な訓練をつんだわけではないが、この森で獣を取る方法ぐらいは熟知している。
それに、魔法を使えない分も、と言うわけではないが剣と弓の取り扱いぐらいは習熟している。
大型の猛獣となればいざしらず、食料となる獣を獲るぐらいであれば問題は無い。
「オックスも手伝ってくれれば楽なんだがな」
同じ狩りをするのでも、一人で行うのと二人で行うのでは手段も効率も変わってくる。
一人であれば忍び寄って獣を射殺すぐらいしかできないが、二人であれば待ち伏せも出来るしさまざまな罠も張れる。
そう思ってオックスにも狩りの手伝いをしてくれるように頼んだのだが、それ返答はと言うと。
「すまん、俺は剣や弓を使えないんだ」
そんな言葉だった。
もちろん、魔術が使えると言うことも無い。
出会ったときに武器や防具の類のものを身につけていなかったのは途中で奪われたり捨てたりしためかと思っていたのだが、聞いてみると元々持っていなかったらしい。
それを聴いて眩暈がした。
よくこの森に入って―――いや、ヴァルカニアを旅して無事だったものだ。
呆れてそう言ってみても、オックスはなんだか複雑な表情で笑うだけだった。
まあ、出来ないと言うのならばしょうがない。
今の時期ならば獣も多いし、木の実も豊富だから二人分の食い扶持ぐらいなら何とかなるはずだ。
そんなわけで俺はオックスに留守を任せ、一人で狩りをしている。
「冬までにはオックスも―――」
何とはなしにそこまで呟き、思わず口を噤む。
冬までにはオックスも回復して森を出て行く。
当然のことだ。
オックスは人間なのだからこの森にはいるべきではない。
それはエルフのしきたりとか、そんなことが理由ではない。
オックスは一つ所にとどまるべき人間ではない。
ただ俺は感覚的にそう思っていた。
「……どちらにしろ、まだ先の話だ」
俺は、こんなに弱かっただろうか。
親や氏族の皆と距離をとると決めた時には、こんなに悩まなかったような気がする。
今とは、明らかに違う。
つまり、俺にとってオックスとの生活は氏族の皆より大切だと言うことか。
確かにオックスとの会話は刺激に富み、様々なことを考えさせられる。
一人で過ごすよりは、比べようも無く有意義だと思われる生活。
俺はそんな生活を―――
ガサッ
草を踏む音で俺の思考は中断した。
前方数十フィートのところに何者かの気配。
獣ではない。音の大きさから判断するに、おそらくは複数。
さらに耳を澄ませば、なにか言葉のような―――その内容こそわからないが、明らかに意思疎通を行っているらしい言葉が聞こえる。
「……敵か」
敵。
それは獣ではない。
愚かにもこの森に迷い込んだゴブリンやコボルドたちを―――そして人間を指す言葉。
しかし、耳に届く言葉は明らかに人間の使うものではない。
森の木々に身を潜め、息を殺して慎重に声のするほうに近づいていく。
木々が生い茂り、薄暗い森の中でじっと目を凝らすと―――
「オークどもか」
数を数えてみると、五匹。
その手には汚らしい戦斧や棍棒を握り、下卑た笑みを浮かべている。
先ほども言ったゴブリンやコボルド、それにオークどもがこの森に来ることがないわけではない。
この森には守りの魔術がかけられているが、それでも偶然迷い込んでくる者たちはいる。
俺がここで過ごすようになってからは初めてのことだが、オックスの件もある。
ひょっとして守りの魔術に何か以上でもあったのかもしれない。
「矢は……十分だな」
矢筒の中には、オークを屠るには十分すぎる量があった。
その中から矢を一本取り出し、弓につがえる。
カラ、と。
矢筒の中の矢が音を立てる。
オークを屠るためにつがえた戦闘用の矢を入れたものとは別の、数本しか入らないような小型の矢筒。
そこには連絡用の鏑矢が入っている。
本来、獣ではなくオークのような『敵』と出会ったらまずこの矢で報告をするのが決まり。
鳥の声に似たその音で氏族の皆は敵の襲来を知ることになる。
そして『敵』を屠るために氏族の者たちが救援に来ることになっているのだが……
「俺一人で、十分だ」
そう、十分だ。
たかがオークが五匹。
森に潜み、矢を射かけた後に切りつければなんとでもなる。
何より、氏族の者たちに助けを求めるというのは果てしなく不快だった。
オークどもの全てを射殺してから報告すれば、それで事足りる。
そう考え、俺は森に潜んで弓を引き絞る。
キリ、とかすかな音を立てた後に矢が放たれる。
「グギャッ!?」
狙いたがわず一匹のオークの肩口に命中。
続けて二射、三射、四射。
俺の弓から放たれた矢は一発残らずオークどもに突き刺さり、その度に汚らしい悲鳴を上げる。
そして俺の矢はその悲鳴が止むまで放たれ続け、そして―――
矢筒には一本の矢すら残さず、空になった。
在り得ない。
俺の射た矢の数は、三十と五本。
オーク五匹にきっちり七本ずつ射かけたのだ。
当たり所が悪かったわけでもない。
数発は確かに首や頭と言った致命的な場所に突き刺さり、オークどもは確かに苦痛の悲鳴を上げていた。
しかし、それだけだった。
オークどもは突然の攻撃に対する怒りを目にたぎらせて恐ろしい雄叫びを上げてはいるが、一匹たりとも倒れ伏してはいない。
矢の雨が止むと、俺の矢の攻撃によるダメージなどまるで無かったかのように雄叫びをあげて矢の発生源―――俺の元へと走り出す。
しかし俺とオークどもの間には数多の樹木があり、俺の元へたどり着くまでにはいくらかの時間がかかるはずだ。
オークどもの強靭さがこれほどのものとは思わなかったが、ここは森の中。
万が一のことを考えて、俺は追撃の困難な場所に陣取っていた。
オークどもが俺のところに到達するには、幾多の倒木を乗り越えなければいけない。
奴らが倒木に手間取っているすきに距離をとり、体勢を整えなおしたらもう一度反撃をする。
俺はそう考えていた。
こんなこともあろうかと、森の中には矢や食料を置いてある『補給小屋』がある。
そこまでおびき寄せればさっきにも増す、百本以上の矢を射かけられる。
しかし、そんな俺の考えをあざ笑うかのようにオークどもは走りよってきた。
倒木を乗り越えたり、迂回したりと言った行動をとらずに一直線に。
オークが戦斧を持ったその腕を高く振り上げ、振り下ろすと倒木は見事に両断された。
木々の合間を駆け抜けると、オークはその戦斧で立ち並ぶ木をなぎ倒しながら追いかけてくる。
獣を捕らえるために仕掛けた罠に誘導したら、その罠は力づくて引きちぎられた。
在り得ない。
こんなことは在り得ない。
確かにオークは頑強な種族かもしれない。
しかし、アレはそんなレベルではない。
障害物を押しのけるのではなく、粉砕し。
自らの邪魔になるものを踏み越えるのではなく、踏み散らす。
アレは、オークではない。
少なくとも俺が知っている、エルフが敵でありながら下等な種族と蔑むあの種族ではない。
アレは、もっとちがう何かだ。
ガツッ
数分の間逃げ回っただろうか。
全力疾走を続けた俺の息は上がり、足がもつれて地に倒れた。
乱れる息を必死に整え、迫り来るオークを見るが、やつらは微塵も疲れた様子を見せない。
やはりアレは違う。
アレは何か、とてもヨクナイモノだ。
奴らは俺が倒れ、立ち上がれずにいるのを見るとニヤリ、と本当に禍々しく笑った。
そしてその口の端から汚らしい唾液をたらしながら、俺の恐怖をあおるように一歩一歩ゆっくりと近づいてくる。
立たないと。
立ち上がって逃げないと。
そう思って立ち上がろうとするのだが、疲れ果てた足は全く言うことを聞いてくれない。
オークどもはじりじりと歩みながら、俺の逃げ道をふさぐように、着実に俺の周囲を囲みだす。
逃げられない。
そう思って絶望し、身じろいだときに矢筒―――救援用の鏑矢の入った矢筒が音を立てた。
氏族の者たちに救援を頼むのは不快である。
だが、それどころではない。
このままでは確実に、俺は虫けらのように踏み潰される。
俺は鏑矢を手に取り、天に向かってその矢を放った。
俺の最後の望みとなったその矢は鳥の鳴き声のような矢を響かせながら、空へと吸い込まれて行く。
「くそっ」
やるべきことはやった。
後は最後まであがくだけだ。
俺は矢の尽きた矢筒と用を済ませた弓を投げ捨て、腰に下げた鞘から剣を抜いた。
ひ弱なエルフが剣を抜いたことが滑稽なのか、オークはその下卑た笑いを深めて俺の方へとにじり寄る。
五匹のオークは舌なめずりをしながら、俺の周囲でそれぞれの武器を構えている。
そしてそのうち一匹が大きく斧を振りかぶった。
慌てて剣を構える。
ガインッ
その斧を一撃受けた瞬間、両腕が利かなくなった。
足元に俺の剣が落ちる。
しかしそれを拾うことすら出来ない。
骨は折れていない―――と、思う。
しかしオークの戦斧を一撃受けただけで俺の両腕には信じられないほどの衝撃が走り、両手の感覚は無くなった。
目の前のオークは俺が剣を落としたのを見ると、またニヤニヤと笑いながら前蹴りを放ってきた。
それをもろに喰らう。
丸太をぶつけられたような衝撃を受け、吹き飛ばされる。
後ろにいたオークにぶつかり、そいつは汚らしいものに触ったかのように俺をその両手で突き倒す。
「ガハッ」
さっきの蹴りで内臓がやられたのだろうか、口から真っ赤な血があふれ出した。
そのまま自分の血溜りに倒れこみ、地と泥にまみれた俺を見るとオークどもはさも愉快そうに耳障りな笑い声を上げた。
憎い。
歯がゆい。
許せない。
オークが許せない以上に、俺の無力さが許せない。
魔術が身につけられないからと氏族から追い出され、一人で暮らして最後はオークの嬲り者にされるのか。
俺をなぶるのに飽きたのか、目の前で斧を高々と振り上げるオークを見ながらそう思う。
俺にもう少し力があれば。
魔術が使えなくても、それを補えるだけの力があればこんな最後は迎えなかっただろうに。
「―――オックス」
あの友は無事でいて欲しいと。
振り下ろされる斧を見ながら最後に思ったのは、そんなことだった。
「呼んだか、サイラン」
そして、そんな声と共に響いたのはまさに轟音。
俺の頭部に振り下ろされようとしていた非常な斧は、それを持っていたオークごとたっぷり5フィートは吹き飛ばされていた。
「……オックス?」
そう、俺の危機を救ったのは。
俺の矢を受けても意に介さず、巨大な倒木をその斧の一撃で粉砕した凶悪なオークを吹き飛ばしたのは。
俺が始めて友と呼んだ、あの男だった。
いつも俺と話していた時のような笑顔で俺を見、俺に声をかける。
「お前の危機を獣から聴いて駆けつけたのだが、細かい場所がわからなくてな。あの矢の音が無ければ間に合わなかったかもしれない」
「オックス、後ろ!」
あくまで飄々と告げるオックスの後ろでオークがその斧を振り上げていた。
慌てて声をかけるが時すでに斧は振り下ろされ―――
「ギャグウッ……」
ることなく、地面に落ちた。
オークの斧が振り下ろされたと思った瞬間にオックスの体が翻り、オークの鳩尾にはオックスの肘がめり込んでいた。
そしてその脚が凄まじい速度で振り上げられる。
「死ね」
オックスの右足はオークの顎先を捉え、その一撃でオークの首はへし折れた。
オックスは武器も防具も身に纏ってはいない。
それどころか本当に普段着のまま、今朝俺と一緒に食事をしたときと全く同じ格好だった。
「すまないが、話は後だ」
そう言ってオックスは、振り上げた脚を静かに下ろして振り返る。
その視線の先にあるのは三匹のオーク。
オークたちはオックスを見るとその顔に始めて緊張をみなぎらせ、油断無くその武器を構える。
そしてオックスは、今まで一度も聴いたことの無い厳しい口調でオークたちに告げた。
「汚らわしいオークども。わが友を傷つけたその罪、死を持って償え」
それは、殺戮だった。
戦いではない。
戦いとは互いの命を奪い合い、傷つけあう行為。
片方が全く傷を負わず、そんな可能性すら感じさせずに敵を屠り続ける。
それは戦いではなく殺戮、言葉を選ぶのと言うのなら、制圧。
そんな言葉しか思い浮かばなかった。
巨木を両断するオークの斧はオックスにかすることすらなく。
その分厚い外皮に守られたオークにオックスはダメージを与え続け。
あまつさえその手足は炎に包まれ、その生命の存在する可能性を欠片も許さない。
慈悲無く容赦なく、オックスの殺戮は絶え間なく続き、数分かけずにオークたちの生命の炎は消え去った。
そしてオックスは全てのオークの絶命を確認すると、一匹の首にかかっていた首飾りを見てその表情をまた歪めた。
「……オックス?」
「ああ。すまない、サイラン」
「いや。危ないところを助けてくれたのはお前なんだから謝る必要は無いと思うが……さっきのは?」
そう、オックスの動き。
それは戦士のものでもなく、もちろんなにか魔術を使ったと言うわけでもないだろう。
オックスはその全てが事前に判っているかのようにオークの斧をことごとく避け、寸鉄すら纏わないその脚と拳と、その肉体の全てをもって繰り出された一撃はオークの命を奪った。
「魔術に頼らずとも、己が肉体を鍛えれば人は人を越せる。こいつらのように他の何かにすがる必要も無い」
俺の問いにそう答えるとオークの死体から首飾りをむしりとり、忌々しげにその首飾りを握り締める。
そしてまたオックスの拳が炎に包まれ、首飾りは砕け散った。
オックスは何かに思いを馳せるように空を見上げて、何かを憎むような、そして同時に何かを悔いるような表情をしてから俺の方へと振り向く。
その表情はいつものような―――俺と森の小屋で過ごしてきた時のような笑顔だったが、何か別な感情を隠していることは明らかだった。
「すまんなサイラン。もう行かなければ」
「何故だ」
俺は判っていた。
オックスの休息は今終わったのだと。
その胸に秘める目的のために旅立つ日が来たのだと。
それでも俺はそれを確認するためにオックスに問いかけた。
そしてオックスは、わが友は隠すことなくその理由を打ち明けてくれる。
「こいつらの目的は私だったようだ」
そう言って首飾りの破片が残る右手を見つめ、何かを振り切るようにその腕を大きく払った。
「ここに来たのも、こいつらの目から逃れるためだった。しかし、ここを嗅ぎ付けられたのなら離れなくてはいけない」
そう言ってオックスは森の外の方を向き、歩みだす。
束の間の休息場所から旅立つために。
そして、俺と別れて旅立つために。
「サイランよ」
さらばだ。
そう言おうとしているのが俺にはわかった。
読心の術など仕えない。
しかし数日の間、共に過ごした俺にはありありと判った。
しかし、それを言わせるわけにいかない。
だから俺はオックスの言葉を遮って声をかける。
「待ってくれ」
「どうした?」
訝しげなオックス。
俺が何を言うのか予想できないのだろう。
それはそうだ。
数分前にはこんなことを言おうと思っていなかったのだから。
それでも、一度言おうと思ったら何の迷いもなく声が出た。
「俺も……お前のようになりたい。連れて行ってくれないか」
「いいのか? 森を出てしまって」
「ああ。考えてみればもっと早くに出るべきだった」
俺の言葉にさすがに驚いたのか、表情を変えるオックスを見て愉快に思いつつそう答える。
振り返ると、先ほどまでの様子は嘘のように静まり返り、いつもと変わらない森が広がっている。
そう。いつもと全く変わることの無い、まるで騒ぎの起きていない森が。
先刻の鏑矢の音で俺の危機が伝わっていないわけがない。
あれはエルフが有事のときに使うための特別製の矢だ。
森の中にいてあの音を氏族のエルフが聞き逃すことなど在り得ない。
そして、ここはエルフの住む森。
いくらオックスが超人的な身体能力を持つとは言え、オックスが駆けつけてからかなりの時間が経っている。
これだけ時間が経っても誰も来る様子が無いと言うことは、おれはいよいよ見捨てられたのだろう。
ひょっとして、今頃は里で防備を固めているのかもしれない。
俺が知らせた危機から身を守るために。
「それに、旅立つとしても食料が無ければ前のように行き倒れるぞ?」
俺がおどけたようにそう言うと、オックスは気づいたようだがそれでも普段と変わらぬ口調で言葉を返す。
「お前の望みなら構わないが、修行は辛いぞ?」
「やり遂げて見せるさ。俺にはもう他に道はない」
そして俺はオックスと力強く握手を交わし、旅立った。
主を失った小屋には何も無い。
備蓄されていた保存食は欠片も残らず、ここの主が好んだ果実酒は全て皮袋に詰められ、持ち出された。
そこに残るのは使い古された寝床と、エルフの氏族の紋章が掘り込まれた指輪のみ。
陽の光を受け、輝いていたはずのその指輪はなぜかその輝きを失い、くすんだように見えた。